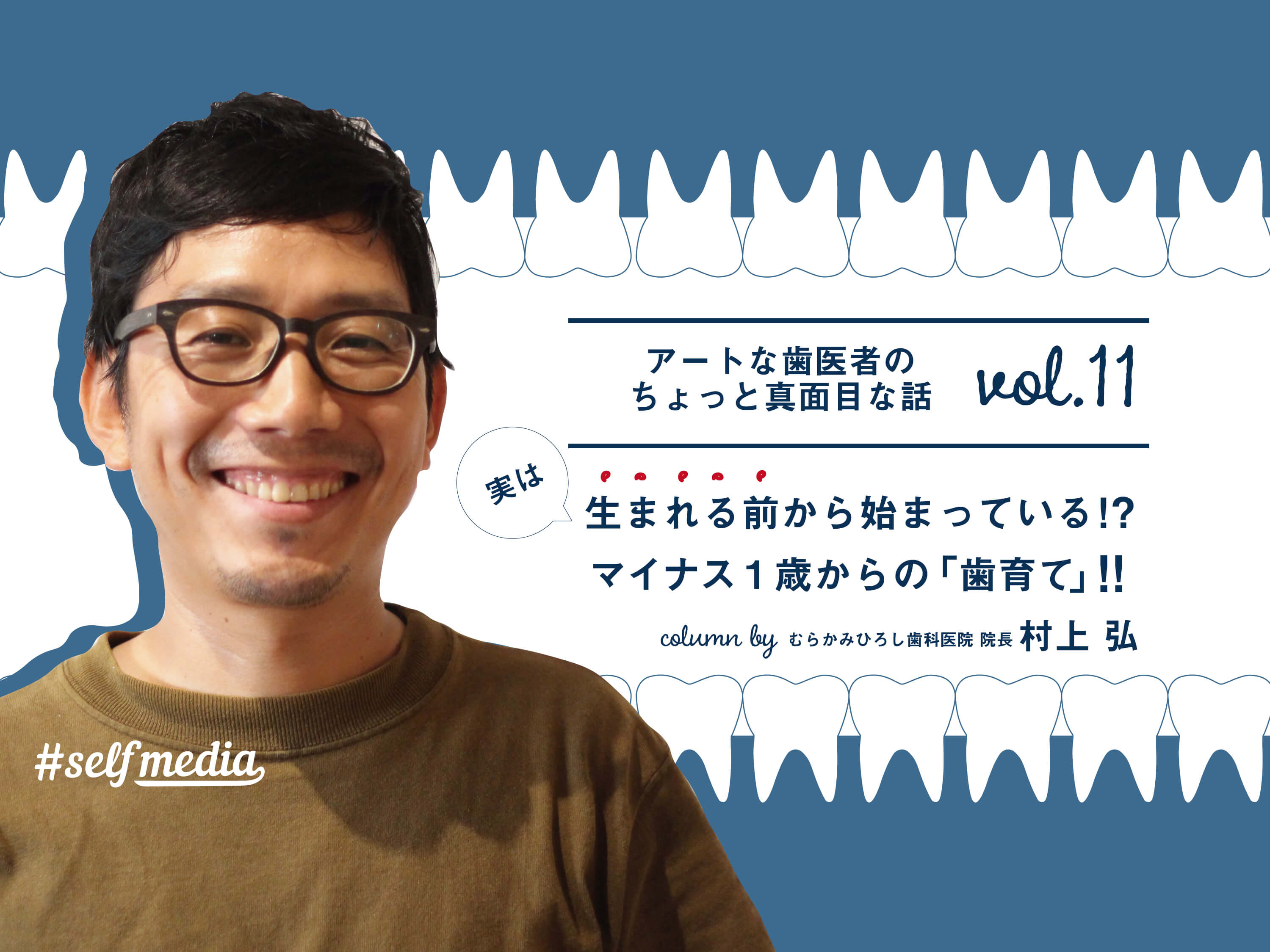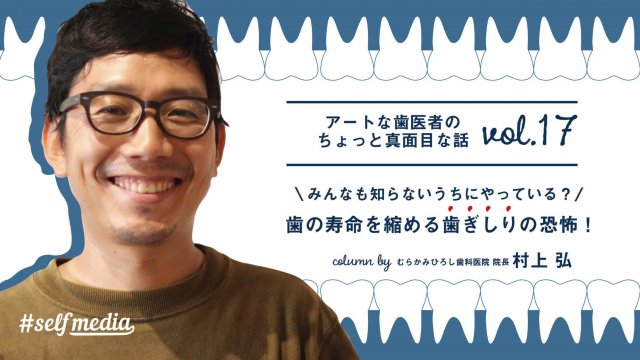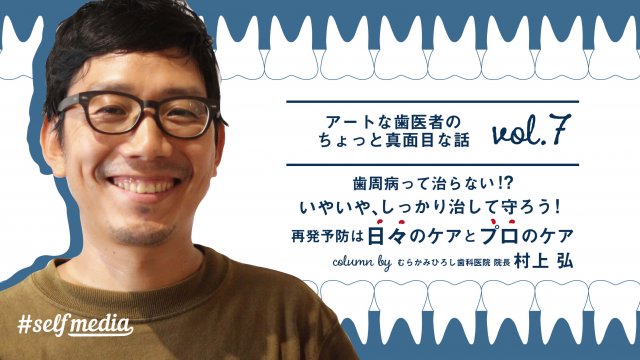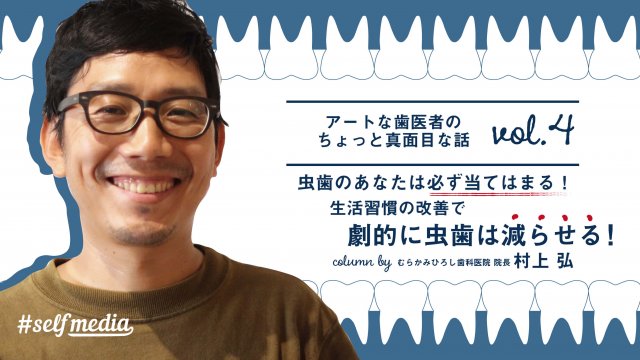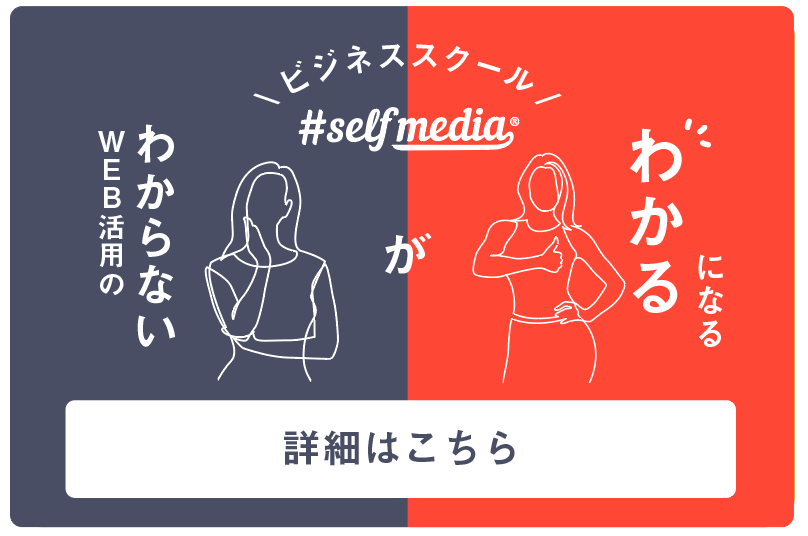実は生まれる前から始まっている!?マイナス1歳からの「歯育て」!!
2020年6月22日
目次
前回のコラムで「歯並び」を決める要素は遺伝的な要因が多くても20%前後で、ほとんどが生活習慣に関わる要因であることを説明しました。
では、子供の「歯並び」を健全に育成するにはいつから始めればいいのでしょうか?
日常でも同じような質問を受けることがありますが、実は私も厳密にいつからとはっきり言えません…。それは影響を与える因子があまりに多すぎるから…。
実は、マイナス1歳から子供の健全な「歯並び」の育成=「歯育て」は始まっています。そこで、今回は子供の成長の段階において、注意すべきことをまとめていきたいと思います。
まずはお母さんの口から

赤ちゃんは、お母さんのお腹の中で300日程を過ごします。その中で少しずつ大きくなるわけですが、その成長過程でお母さんからの影響を大きく受けます。
つまり、健全な赤ちゃんの「歯育て」もお母さんから始まるのです。
歯周病を治そう!
お子さんをお持ちの方はご存知だと思いますが、母子手帳には歯科検診のページがあります。
一体、なぜでしょう?
実は、お腹の赤ちゃんの成長と歯周病とは大きな関わりがあるのです。
歯周病は早産のリスクを2.27倍に引き上げ、低体重児のリスクを4.03倍に引き上げまます。タバコやアルコールもお腹の赤ちゃんに影響があると言われていますが、歯周病ほどリスクは高くないというのが事実です。
妊娠前・中にしっかりと歯周病のケアを行うことでお腹の赤ちゃんを元気に大きく育ててあげましょう!
虫歯を治そう!
虫歯が子供の歯並びに影響することは、前回のコラムでも少し触れさせていただきました。乳歯は永久歯の道しるべとなり、虫歯があるとその道しるべとしての機能を果たせません。
では、その虫歯はどうやってできるのでしょうか?
これも以前のコラムでお話させていただきましたが、虫歯の成り立ちには虫歯菌の存在が欠かせません。
それでは、そもそもその虫歯菌はどこから来るのでしょうか?
実は、子供に定着する虫歯菌の60〜70%が母親由来のものであることがわかっています。子育ての中でお母さんが一番身近な存在であり、お母さんの口から虫歯菌が定着するのは仕方がないことかもしれませんね。なので、お母さんを含めた周りの大人の口の中の虫歯菌を減らすことが一番有効なのです。
赤ちゃんの歯が生え揃う1歳半までにはしっかり虫歯を治して、虫歯菌の少ない口の中を維持しましょう!
なるべく正しい姿勢で過ごそう!
妊娠も20週を超えて来るとお腹の赤ちゃんもかなり大きくなってきます。この頃になると、指を吸ったり、飲み込んだりといった生後1年間に必要な機能の練習をするようになります。
お腹の赤ちゃんは、お母さんの限られたお腹の中でその練習をするわけですが、その空間はお母さんの姿勢で大きく左右されます。お母さんの姿勢が悪ければ、子宮の形態が悪くなり、赤ちゃんの体勢も悪くなり、正しい成長を促すことが出来なくなります。
椅子に座る時は、あまり深く腰掛けずに足の裏で体重を支えて、なるべく猫背にならないように姿勢を保ちましょう!
哺乳で意識する「歯育て」
哺乳の目的は、赤ちゃんが栄養を蓄えるために必要な行動なのですが、実はそれだけではありません。
赤ちゃんは、哺乳時に舌をベッタリと上アゴにくっつけながらおっぱいを吸っています。この舌の動きで上アゴが横に広がり、正常な上アゴの成長を促すのです。
正面からおっぱいを吸わせましょう!
できるだけ赤ちゃんが正面から吸い付けるように抱いてあげましょう。そうすることでまっすぐおっぱいを吸うことができて、左右均等な筋肉のバランスを保たれるのです。
バランスの良い唇の周りの筋肉と頬の筋肉が作られ、左右バランスの良いアゴの成長を促すことができるのです。
もし、正面からの授乳が難しい場合は、片方だけに偏らないように左右バランス良く吸わせるだけでも十分効果があるのでバランスを大事にしてみてください!ながら授乳はなるべく控えましょう!
なるべく縦に抱いて足底接地!
赤ちゃんは搾り出した母乳を飲み込み、食道・胃へ送り出します。
想像してみてください、寝転がって首をひねった状態では飲み込めませんよね!?赤ちゃんも同じですね。頭を支えながら、なるべく縦に抱っこして飲み込みやすい体勢を維持してあげましょう。
また、抱っこしている時はできるだけ赤ちゃんの足の裏が腕や手に触れた状態にして抱っこしてあげてください。足の裏で踏んばれる状態(足底接地)であることで体の軸が真っ直ぐになって飲み込みを上手に覚えることができるのです。
赤ちゃんが飲み込みやすい姿勢で、正しい筋肉の使い方を憶えて正常なアゴの成長を促してあげましょう!もちろん、哺乳瓶を使う時も同じです!
離乳食で意識する「歯育て」

下の前歯が生え始める(6ヶ月〜8ヶ月)と離乳食を始める時期のサインです。
母乳から卒業して人間本来の噛んで食べることを憶える準備を始める重要な時期に入ります。栄養の取り方が液体から半固形物へと変わるだけではなく、口の機能の発達にも関わるので「歯育て」を意識してみてください。
スプーンはまっすぐに!
まずはスプーンを赤ちゃんの口の近くにまっすぐに運びましょう。いい匂いがしたり美味しそうなものを見ると赤ちゃんは本能的に食べたくなり、口を開け、前に出して目の前のものを捕食(=物を捉えようとする)しようとします。
ゆっくりとスプーンを下唇の先まで進めてあげましょう、赤ちゃんは上下の唇を使ってしっかりと口の中に入れようとします。
ここで注意しなければならないのは、上唇や上の前歯の裏側に無理に擦り付けないようにしましょう!つかみ取るというのが大切です!
赤ちゃんの下唇にまっすぐ差し出し、赤ちゃんがつかみ取った後にまっすぐ引くことが重要です。これで唇の力をトレーニングして、食べ物の大きさや硬さを認識する感覚を養うこと意識しましょう!
ゆっくり焦らずに!
赤ちゃんは口の中に入った少量の離乳食を舌の動きで口の奥の方に送り、最後にごっくんと飲み込みます。この一連の流れのなかで、食べ物の硬さを認識し、舌と上顎・歯と歯で味わいながら咀嚼=噛むことを憶えていきます。
そして、口の中で咀嚼を行い唾液と食べ物を良く混ぜて食塊=飲み込める状態の食べ物を作り、喉まで送って嚥下=飲み込むことを憶えるのです。
赤ちゃんはこの咀嚼→嚥下を自分のペースで少しずつトレーニングしていきます。このペースを無視して、タイミングを考えずにどんどん口の中に入れていくと早食い・丸飲みを誘発してアゴの成長を妨げる結果になってしまいますので注意しましょう!
赤ちゃんがしっかり飲み込んで、口の中が空っぽになってから次の離乳食を持っていってあげましょう!
呼吸と姿勢を意識して!
くちゃくちゃと口を開けて食事をしている子を見たことはありませんか?
これも、正しく離乳食によるトレーニングができてない子に多いようです。口でゆっくり食事をするためには鼻呼吸と姿勢が重要なのですが、これが出来ていないと食べながら口呼吸をしなくてはいけないのでくちゃくちゃ音が出てしまうのです。
離乳食を食べる時には、頭位・体幹・呼吸の安定のため、体の軸をまっすぐにし、足底がしっかり地面に接地した姿勢(足底接地)が重要です。腰がすわって、自分で座れるようになってきたら両足がしっかりとついて、ふんばりがきくようなイスに座らせてください。
赤ちゃんも大人も姿勢は大事です。寝転がったままではうまく食事も呼吸も出来ません。姿勢を意識して呼吸がしやすい環境で離乳食を楽しみましょう!
気負わずに出来ることから!

子供の「歯育て」は、お母さんのお腹の中にいる時から始まっています。しかし、なかなかストイックにすべてのことを完璧にこなすことは難しいですね。
私も中1と年長の男の子の二人の父親ですが、振り返ってみるとそんなにストイックには出来ていません。しかし、要所で最低限必要なことはしてきたつもりです。今のところ、二人ともさほど問題なく「歯育て」が出来ていると思います。
「気負わずに出来ることを楽しみながら」
こんなスタンスでいくといいのではないでしょうか?
小さい時から歯科医院に定期的に行くことで、気付かなかったポイントも見つかるかもしれません。
「歯育て」のわかるかかりつけ歯科医院を見つけて、親子でケアすることをオススメします!わからないことは専門家に聞いてみましょう!
今回のコラムでは、マイナス1歳から1歳くらいまでの「歯育て」についてお話しました。
次回のコラムでは1歳から3歳くらいまでの「歯育て」についてお話したいと思います。ぜひ、お楽しみに!
アートな歯医者のちょっと真面目な話、ぜひこれも読んで欲しい!!!
https://selfmedia.club/column/tooth/murakami09/
https://selfmedia.club/column/tooth/murakami06/
https://selfmedia.club/column/tooth/murakami03/
« 第4回#selfmedia for friends講義 学生でも分かる!webセールス講義 イギリス留学経験者が語る、留学を成功させるための2つの鍵! »